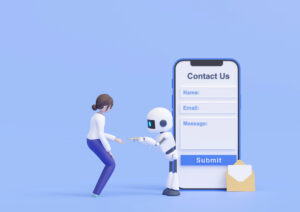-
- 投稿日
- 2025.04.28
-
- 更新日
- 2025.04.28
ナレッジマネジメントとは、社員がそれぞれ持つ知識やノウハウを組織で共有・活用し、新たな知識を創造する仕組みです。
社内で導入すると、業務の属人化を解消できるため、生産性の向上や業務効率化が期待できます。
本記事では、ナレッジマネジメントの概要やメリット、導入手順などについて解説します。
ナレッジマネジメントの推進を検討中の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ナレッジマネジメントとは?
ナレッジマネジメントとは、社員一人ひとりが業務で培った知識や経験、ノウハウといった知的資産を組織全体で共有し、活用することで、新たな知識を創造する手法です。
個人の持つ貴重な知識を誰もが理解できる形に変換して蓄積・共有すれば、業務効率化や属人化の解消、さらには組織全体のスキルアップやイノベーション創出へとつなげることが可能です。
近年、働き方の多様化や人材の流動化が進む中で、個人の知識を組織の財産として蓄積・活用するナレッジマネジメントの重要性はますます高まっています。
単なる情報共有にとどまらず、組織全体の成長を促す戦略的な取り組みとして注目されている考え方です。
ナレッジマネジメントが注目されている背景
近年、ナレッジマネジメントが注目されるのは、主に次の2つの背景が挙げられます。
雇用の流動化でナレッジの継承が難しい
1つ目は、雇用の流動化により、個人が持つナレッジの継承が難しくなってきたことが挙げられます。
かつては企業に新卒で入社したら、定年まで働き続けることが一般的でした。
先輩が持つ知識やノウハウ、こつなどは、時間をかけて自然と後輩に受け継がれていきました。
しかし、現在は終身雇用制度が崩壊しつつあり、働き方も多様化しています。
転職も珍しくはなくなったため、かつてのような長期的な人材育成は難しくなっています。
人から人へと知識やノウハウを受け継ぐのが難しくなった現在は、社員が持つナレッジを組織で集約し、管理・活用できるように取り組む企業が増えています。
ナレッジを言語化して共有すれば、特定の業務に精通した社員が退職しても、別の社員がスムーズに業務を引き継げます。
業務の属人化にはリスクがあるため
2つ目は、業務の属人化を防ぐためです。
特定の社員しかできない仕事があると、不在時に他の社員が対応できず、業務が停滞します。
顧客への対応も遅れるため、顧客満足度が低下する恐れもあります。
特定の社員に業務を依存すると、その社員がナレッジを継承せずに転職するリスクもあるため、属人化の解消は多くの企業の課題です。
業務に必要な知識やノウハウを個人にとどめず社内で集約して活用すれば、業務の属人化を解消できます。
業務標準化の体制を整えることで、担当者の不在時や退職時も業務が滞ることがありません。
ナレッジマネジメントのメリット
ナレッジマネジメントを導入すると、主に次のようなメリットがもたらされます。
業務効率化
1つ目のメリットは、業務効率化です。
個々の社員が持つ知識や経験を組織内で共有すれば、スムーズな業務遂行が可能になり、時間コストの大幅な削減が可能です。
業務内容や手順をマニュアル化すれば、誰もが必要な知識を得られるため、不明点を自身ですぐに解決できます。
知識を持つ社員が質問への対応に時間を費やすこともなくなるため、業務効率化が図れます。
また近年はテレワークの導入により、オフィスの外で仕事をする機会が増えてきました。
テレワークの環境でも、社員は自ら必要な情報を探して問題を解決できます。
簡単に質問できない状況でも業務が滞ることがないため、業務効率が向上するでしょう。
組織力の強化
2つ目のメリットは、組織力の強化です。
ナレッジ管理によって組織内で知識やノウハウを共有すれば、業務の属人化を解消できます。
特定の業務が一人の社員に依存する状態を回避できるため、担当者の不在時や休職・退職による業務停滞を防げます。
また他部署の知見を共有できるため、新しいアイデアが生まれやすくなり、イノベーションの創出につながりやすくなるでしょう。
人材育成の効率化
3つ目のメリットは、人材育成の効率化です。
社員個人が持つノウハウを社内で活用しやすいように集約すれば、必要な情報に誰でもアクセスできます。
新入社員は分からないことがあっても、毎回先輩社員や上司に質問する必要がなくなります。
育成する側も新入社員に付きっきりで指導する必要がなくなるため、人材育成にかかる時間や労力を大幅に削減できるでしょう。
顧客満足度の向上
4つ目のメリットは、顧客満足度の向上です。
顧客対応に役立つ知識やノウハウを集約しておくと、いつでも必要なときに素早く引き出せます。
顧客対応の標準化や対応品質の向上が図れるため、顧客満足度が向上するでしょう。
ナレッジマネジメントにおける暗黙知・形式知とは?
ナレッジマネジメントにおける重要な概念に「暗黙知」「形式知」があります。
それぞれの意味を解説します。
暗黙知
暗黙知とは、経験や直感に基づく言語化が難しい知識を意味します。
ベテラン社員や熟練した技術者が長年の経験で培った感覚的なスキルやこつは、言葉で説明するのが困難です。
例えば優秀な営業スタッフが持つスキルは文書化されていない場合が多く、他の社員に共有されていないことが少なくありません。
暗黙知のままでは他人に継承できないため、組織全体のスキルの底上げも難しいでしょう。
知識が個人の中に埋もれてしまうため、離職した場合に知識を組織に蓄えておけません。
形式知
形式知とは、知識を誰でも理解できるように言語や数字、表などを用いて表現したものです。
例えば、マニュアルや作業手順書などが該当します。
形式知は知識が個人の中に埋もれてしまうことがないため、社内で誰でも活用できます。
ナレッジマネジメントの理解に必要な4つの要素
ナレッジマネジメントの考え方を知るには、先述の2種類の知識「暗黙知」と「形式知」に加え、次の4つの要素を理解する必要があります。
- SECIモデル
- 場
- 知識資産
- ナレッジリーダー
それぞれの内容を解説します。
SECIモデル
SECIモデルとは、暗黙知を形式知へ変換し、新たな発見を創出するためのフレームワークです。
変換過程の頭文字を取ってSECIと呼ばれています。
SECIモデルは、次の4つのプロセスによって暗黙知を形式知へ変換・移転し、新たな暗黙知を生み出します。
1. 共同化(Socialization)
1つ目の「共同化」は、共通の体験を通して暗黙知を他社に伝達する過程です。
この段階では、まだ知識が形式知化されていないため、言葉でうまく伝えることができません。
経験に基づく知識の共有は、体を動かしたり五感を使ったりしなければ難しいため、同じ体験をして知識を伝達します。
OJTなどが共同化に該当します。
2. 表出化(Externalization)
2つ目の「表出化」は、獲得した暗黙知を形式知に変換する過程です。
マニュアル化などが表出化に該当します。
言葉や図表、映像などを使って形式知にします。
3. 連結化(Externalization)
3つ目の「連結化」は、形式知を組み合わせることによって、新たな知識を創造する過程です。
チームや部署で個別に作られたマニュアルをまとめて、新たにマニュアルを作成したり、他部署の成功事例を参考にして新しいアイデアを生み出したりすることなどが連結化に該当します。
4. 内面化(Internalization)
4つ目の「内面化」は、連結化で生まれた形式知を実践し、自分のものにする過程です。
例えば、マニュアルを基に業務を行い、自分自身で新たな気付きを得ることなどが内面化に該当します。
知識として理解するだけでなく、実践によってこつをつかんで業務の質が向上すると、自身の暗黙知へと変化します。
SECIモデルは、暗黙知が形式知となり、再び個人の暗黙知となる流れです。
この4つの過程を繰り返すことによって、組織の知識資産が蓄積されていきます。
「場」
「場」とは、知識を創造し、共有や活用される環境のことです。
暗黙知や形式知に対して、適切な場を作ることが重要だと考えられています。
「場」が指すのは物理的な場所だけではありません。
休憩所での雑談や社内SNS、オンライン会議なども含まれます。
マニュアルを読んで知識を身に付けても「場」でうまく適用できないことがあるため、効果的な場の整備が重要です。
適切な場では暗黙知と形式知の交換や共有・連結が促され、新しい価値の創造につながります。
SECIモデルにはそれぞれのプロセスに適した4つの場があります。
創発場
共同化のプロセスで、知識の交換を行う場です。
OJTのような共同作業だけでなく、職場での雑談やランチ会、飲み会など気軽なコミュニケーションでの知識の交換も該当します。
対話場
表出化のプロセスで、暗黙知を形式知に変換する場です。
ミーティングや会議でのディスカッションのように、通常業務の中で行われます。
システム場
連結化のプロセスで、形式知が組み合わせられる場です。
新たなアイデアを生み出せるように、資料を持ち寄って話し合うのが望ましいです。
対面でもオンラインでも構いませんが、オンラインミーティングの方が資料を共有しやすいメリットがあります。
実践場
内面化のプロセスで、新たに創出された形式知を実践して知識を習得し、暗黙知へと変換します。
自身の作業スペースで行えるため、特別な場所は必要ありません。
知識資産
知識資産とは、業務上で得た知識やノウハウ、技術、人脈など会社の強みとなる幅広い知識や経験です。
目には見えませんが、企業にとってなくてはならない重要な資産のため、継承していく仕組み作りが重要です。
知識資産は以下の4種類に分類されます。
- 経験的知識資産:社員の経験によって得られるスキルやノウハウ
- 概念的知識資産:組織の方向性を示す経営理念やビジョン
- 体系的知識資産:体系化されたマニュアル
- 恒常的知識資産:組織の日常業務に存在する業務フロー
これら知識資産の創造・蓄積・活用によって、企業は持続的に成長できます。
ナレッジマネジメントを効果的に実践するには、企業理念を明確にして組織全体で共有し、知識を共有するための仕組みを整えることが重要です。
ナレッジリーダーシップ
ナレッジマネジメントに取り組んだからといって、すぐに社内で定着するわけではありません。
導入して成果を出すには、リーダーシップを発揮できるナレッジリーダーの存在が必要です。
ナレッジリーダーは、リーダーとしての役割を認識し、ナレッジを共有しやすい仕組み作りに取り組む必要があります。
知識ビジョンを創り、効果的な場を作って知識を活性化させ、組織を引っ張っていくことが重要です。
また、ナレッジマネジメントはツールを使用するため、リーダーはツールの使い方も熟知しておく必要があります。
ナレッジマネジメントの4つのタイプ
ナレッジマネジメントには、次の4つのタイプがあります。
- ベストプラクティス共有型
- 専門知ネット型
- 知的資本型
- 顧客知共有型
それぞれの特徴を解説します。
1. ベストプラクティス共有型
ベストプラクティス共有型とは、企業内の成功事例や優秀な社員の知識・行動パターンを集約して言語化し、組織内に共有して業務改善などに役立てる手法です。
組織全体のスキルアップを図れます。
2. 専門知ネット型
専門知ネット型とは、専門知識を持つ人たちをネットワークで結び、ナレッジを集約してデータベース化する手法です。
例えば、FAQシステムや社内Wikiなどが専門知ネット型に該当します。
ヘルプデスクや情報システム部など組織内外から問い合わせが多い部署で、課題の迅速な解決や対応品質の向上が期待できます。
3. 知的資本型
知的資本型とは、企業の持つ知的資産を多角的に分析し、経営戦略に活用する手法です。
知的資産とは特許や著作権、ブランドなどの目に見えない資産です。
上手に活用すれば、新たなビジネス機会の創出や収益の向上につながります。
4. 顧客知共有型
顧客知共有型とは、顧客との知識の共有や提供を継続的に行う手法です。
顧客から寄せられた問い合わせや意見、アンケート回答、クレームなどの履歴をデータベース化し、顧客対応の品質向上を図ります。
顧客対応履歴を蓄積すれば、同じような問い合わせに対してスピーディーな対応が可能になります。
また、部署間でデータベースを共有すれば顧客対応の統一や業務品質の向上が実現し、顧客満足度向上につながるでしょう。
ナレッジマネジメントを導入する手順
ナレッジマネジメントは無計画に導入しても組織に浸透せず、期待したような効果を得られない可能性があります。
導入する際は、最初に目的を明確にしましょう。
導入する際の手順や方法を解説します。
1. 目的を明確にする
最初に、何のためにナレッジマネジメントを導入するのか目的を明確にしましょう。
目的を明確にせずに取り組めば、社内の情報を集めるだけになってしまいます。
それでは、業務の改善につながりません。
目的に加えて目標も定め、導入にどのようなメリットがあるか全社員に説明しましょう。
2. 共有したいナレッジの選定
ナレッジマネジメントの目的を明確にしたら、目的を達成するためにどのようなナレッジを集約するかを決めましょう。
社員が業務を進める上で、具体的にどのようなことに困っているかを収集し、業務上の課題をまとめておくと必要な情報を把握しやすくなります。
必要な情報が分かれば、共有すべき情報とそうでない情報が明確になります。
社員もどの知識を共有すれば良いか迷わなくてすむため、ナレッジの集約がスムーズに進むでしょう。
3. 目的に合ったツールを選定する
次は、ナレッジの共有方法や運用の仕方を決めます。
主な方法にはExcelを活用する方法とツールを利用する方法があります。
Excelは普段から利用する機会が多い身近なツールのため、スムーズに導入できて操作方法も分かりやすいです。
ただし、蓄積したナレッジを活用しやすいように分析や共有するのは難しいため、知見を生かしきれないかもしれません。
一方、ツールやシステムは、多様なものが提供されています。
例えば、知識の共有に利用するのであれば社内SNSや社内Wikiなど、知識を活用するならFAQシステムやエンタープライズサーチなどがあります。
自社の課題解決につながるツールを選びましょう。
4. 定期的に見直す
ナレッジマネジメントは、運用開始後も効果が出ているか定期的に見直しが必要です。
社員へのアンケート調査などを行い、ナレッジの蓄積や共有が進んでいるか確認しましょう。
もし進んでいない場合は原因となっている課題を解消し、ナレッジを共有して活用することの重要性を再度社内に周知しましょう。
ナレッジマネジメントを成功させるポイント
最後に、ナレッジマネジメントを成功させるためのポイントをご紹介します。
導入前に社員へ目的を周知する
ナレッジマネジメントは個々の社員が持つ知識やノウハウを集約して活用するため、導入を成功させるためには、社員の協力が不可欠です。
そこで導入前に、なぜ取り入れるのか理由や目的の周知が大切です。
導入すればどのようなメリットがあるのかを説明すれば、社員の理解や協力を得やすくなります。
知識を共有したくなる仕組みを作る
ナレッジマネジメントの導入を成功させるには、自身の知識やノウハウを共有したくなる仕組み作りも重要なポイントです。
なぜなら優れた知識やスキルを持つ社員がナレッジ共有に積極的ではないケースもあるからです。
優秀な社員は日々多忙を極めるため、知識を共有するために時間を割くのが難しい可能性があります。
そのような場合は、移動時間にツールを利用してナレッジを入力できるよう、タブレット端末を支給すると良いでしょう。
また自分が培ったノウハウは評価に直結するため、他の社員と共有することにメリットを感じられない人もいます。
このようなケースの対策としては、ナレッジ共有を評価制度に組み込む方法が効果的です。
個人の成果が評価に直結する成果主義は、自分の成績が何より重要となるため、協力を拒むことにつながりかねません。
売上だけでなく、マニュアルの作成や後輩の育成などを評価項目に入れることで、知識やスキル、ノウハウの共有が進むでしょう。
ナレッジマネジメントは現代のビジネス環境に不可欠
ナレッジマネジメントとは、社員がそれぞれ持っている知識や経験を社内で共有し、活用して新たな知識を創造する手法です。
個々の社員が自分自身で培ったノウハウやこつを他の社員にも共有すれば、組織全体の生産性向上が期待できます。
ただし、誰もが自分の知識を喜んで提供してくれるとは限りません。
特に優れた知識やスキルを持つ優秀な社員の場合、自分の経験で培った知識やノウハウを提供して共有することに抵抗があるかもしれません。
そのため、社員が積極的にナレッジを提供できるよう、評価制度の工夫などを検討しましょう。
導入の際は、自社の目的に合ったツールを導入すれば、ナレッジの共有や活用がしやすくなります。
例えば、ナレッジの活用にチャットボットを導入すると、業務効率や顧客対応の向上が期待できます。
Difyはプログラミングの知識がなくても、AIチャットボットなどの生成AIアプリを構築できるツールです。
RAGによるナレッジ機能を利用できるため、社内資料やデータを参照して正確な情報を回答するチャットボットを作ることも可能です。
ナレッジマネジメント推進のためAIチャットボットを導入しようか検討中の担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
 山本 豊
山本 豊Difyライセンス・支援サービスの営業責任者。
連絡先:dify@tdse.jp

お問い合わせはこちら

資料ダウンロードはこちら