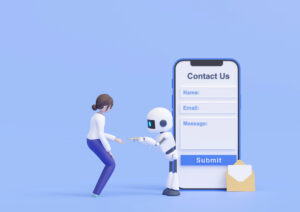-
- 投稿日
- 2025.03.27
-
- 更新日
- 2025.03.27
ナレッジベースとは、社内で知識やノウハウを管理・共有するデータベースです。
一部の社員だけが業務に有益な知識を持つのではなく、会社全体で共有して活用できるため、生産性や業務品質の向上、業務効率化が期待できて、属人化も防げます。
本記事では、ナレッジベースの活用事例や代表的なツールなどを解説します。
ナレッジベースの導入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ナレッジベースとは
ナレッジベース(知識ベース)とは、業務で得られた経験やノウハウなどを一元的に集約し、検索して活用しやすい形にしたデータベースです。
ナレッジデータベースと呼ばれることもあります。
企業にとって価値ある知識や技術、経験などが蓄積された知的財産であり、社内でのみ利用されるのが一般的です。
ナレッジベースに集められた知識は、社員全員で共有されます。
新たな知見があれば、社員が容易に情報を追加できるのが特長です。
各社員が持っている経験やノウハウをデータベース化し、他の社員が検索・閲覧しやすいようにすることで、社員個人の能力向上だけでなく、会社全体の業務効率化や人材育成にも役立ちます。
ナレッジマネジメントとの違い
ナレッジマネジメントとは、業務で得た知識を業務に活用できるように管理し、それによって企業の競争力を高める経営手法のことです。
ナレッジベースと混同されやすいですが、両者には明確な違いがあります。
ナレッジベースは、ナレッジマネジメントに必要な知識を蓄積し管理するシステムです。
一方、ナレッジマネジメントは、個人の持つ知的資産を見える形にし、企業で管理・共有する経営手法を指します。
つまり、ナレッジマネジメントは経営手法の一つであり、ナレッジベースはその過程で利用されるツールといえます。
ナレッジベースが注目される背景
近年、ナレッジベースが注目されるようになった背景には、主に以下の2つが挙げられます。
- IT技術の発達
- 知識の継承が難しくなったため
1. IT技術の発達
1つ目は、IT技術の発達です。
かつては紙ベースで知識やノウハウを蓄積していたため、スムーズな共有が困難でした。
近年は、IT技術の発達によって、知見をデータベース化して共有できるようになりました。
また、クラウド技術によって、インターネット環境があればどこにいてもスマートフォンやタブレットなどのデバイスで、必要な情報にアクセスできます。
IT技術が進歩してナレッジを蓄積・共有しやすくなり、検索のしやすさも向上しました。
2. 知識の継承が難しくなったため
人材の流動化や働き方の多様化により、経験に基づく知識の継承が難しくなっていることが、ナレッジベースが注目される背景の一つです。
企業が蓄積する知識には、個人の経験や勘に基づく言語化が難しい「暗黙知」と、文章や図などで表現された「形式知」があります。
以前は、長期雇用が一般的だったため、暗黙知は時間をかけて人から人へ伝えられていました。
しかし、転職が一般的になり、人材の入れ替わりが激しくなった現代では、暗黙知のままでは知識の継承が困難です。
また、リモートワークの普及などにより、対面でのコミュニケーションや情報共有の機会が減ったことも、知識継承を難しくしている要因です。
そのため、暗黙知を形式知に変換し、組織全体で共有・活用できるナレッジベースの必要性が高まっています。
ナレッジベースの活用事例
続いて、ナレッジベースの活用事例を3つご紹介します。
1. 自動音声応答装置
ナレッジベースは、問い合わせ窓口の自動音声応答に活用されています。
ナレッジベースを活用すれば、利用者のダイヤル操作や音声認識によって問い合わせ内容を判別し、適切な対応へと振り分けることが可能です。
また、過去の問い合わせややり取りの内容を知識として蓄積し、よくある問い合わせを音声ガイダンスで対応することで、担当者の負担軽減にもつながるでしょう。
具体的には、コールセンターへの着信、飲食店やホテルの予約、資料請求の受付などで使われています。
電話による問い合わせだけでなく、LINEやウェブサイトのチャットにおける自動メッセージ応答にも、ナレッジベースが活用されることが一般的になってきています。
2. FAQシステム
FAQシステムは、利用者から寄せられる「よくある質問」とその回答をまとめたものです。
頻繁に寄せられる質問と回答をナレッジベースに蓄積しておけば、利用者は電話で問い合わせることなく疑問を解消できます。
また、問い合わせ件数が減り、担当者の負担軽減にもつながるでしょう。
社内向けのFAQシステムや社内wikiも、同様にナレッジベースを活用できます。
例えば、新入社員が抱きやすい疑問や社内規則などをまとめておけば、他の社員に質問せずとも、自分で解決できるようになります。
特に、情報システム部、総務部、人事部など、他部署からの問い合わせが多い部署では、社内FAQシステムに「よくある質問」を蓄積しておくことが効果的です。
社員が自分で回答を探せるようになるため、問い合わせ対応にかかる時間を大幅に削減できるでしょう。
3. エンタープライズサーチ
エンタープライズサーチとは、社内のさまざまなデータや資料を保管場所に関係なく、横断的に検索できるシステムです。
エンタープライズサーチには、ナレッジベースが利用されます。
膨大なデータから必要な情報を素早く検索できるため、業務効率化やスムーズな情報共有が可能です。
また、エンタープライズサーチは資料やデータの最終更新者が表示されるため、社内で誰が詳しいかを可視化できます。
詳細を質問したいときや、知見が必要な業務に適した人材を見つけたいときなどにも活用できるでしょう。
ナレッジベースを導入するメリット
ナレッジベースの導入で得られる主なメリットを4つ挙げます。
1. 他の部署との情報共有がスムーズになる
ナレッジベースを導入すると、部署の垣根を越えて情報共有できるため、他の部署の成功体験を参考にすることも可能になります。
また、現在進んでいるプロジェクトの情報を共有すれば、より協力やすくなるでしょう。
2. 属人化を防いで業務効率化できる
業務が属人化するとさまざまなデメリットがあるため、多くの企業が属人化の解消に取り組んでいます。
マニュアルや業務フローなどをナレッジベースに蓄積すれば、業務の属人化を防げます。
ベテラン社員の暗黙知をナレッジベースに形式知へとして保管すれば、ノウハウを社内で生かせるため、業務効率化が可能です。
業務の引き継ぎもしやすくなるため、担当者の休職や、突然の退職にも備えられます。
業務上で生じた疑問は自己解決できるため、質問や確認にかかる時間も削減できます。
3. 新人教育や社内異動の引き継ぎがスムーズになる
新たに入社した社員への教育がスムーズに進むこともメリットの一つです。
ナレッジベースに蓄積された知識やノウハウに自らアクセスすれば、業務に必要なナレッジを身に付けられます。
近年は人材の流動化が進み、新人教育が課題となっている企業も多いでしょう。
ナレッジベースを導入すれば、人材育成のコストを削減できます。
社内異動で引き継ぎが必要なときも、異動する社員が知識やノウハウを残しておけば、スムーズに引き継ぎできます。
4. 顧客対応の品質を向上できる
ナレッジベースを導入するメリットとして、顧客対応の品質を向上できる点も挙げられます。
例えば、FAQシステムに活用した場合、顧客からの多様な質問や要望に対し、迅速かつ的確な回答を提供することが可能です。
例えばコールセンター業務では、ナレッジベースを活用した情報共有ツールを導入することで、経験が浅いオペレーターでも適切な回答を提供できます。
対応スピードを高め、提供される情報の正確さと一貫性を保てるため、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
ナレッジベースの作り方
ナレッジベースを作るには、主に2つの方法があります。
1つ目は、ExcelやWord、Googleスプレッドシートなど既存のツールを活用してデータベース化する方法です。
既存のツールを使えば、普段から使い慣れているため手軽な上に、導入コストを抑えられます。
一方、大量のデータを扱う場合に検索しにくいことや、セキュリティの問題などがあることに注意が必要です。
2つ目は、ナレッジマネジメントツールなどの専用ツールを使う方法です。
専用ツールを使えば入力や編集、管理や共有などを簡単に行えます。
検索性にも優れているため、ナレッジを効率的に活用できます。
ナレッジベースを構築するツール
ナレッジベースの構築に利用できる代表的なツールを6つご紹介します。
それぞれ特徴が異なるため、目的に合わせて使い分けましょう。
1. データベース
データベースとは、一定のルールに基づいて整理された膨大なデータの集合体です。
蓄積した情報の中から、必要な情報を検索できます。
紙やExcelでのデータ管理に比べると、データベースは膨大なデータを管理できる上に、必要なデータをすぐに取り出せます。
2. グループウェア
グループウェアは、チャットやメッセージ、スケジュール管理、ファイル共有などの機能でコミュニケーションを図れるツールです。
情報やノウハウを共有すれば、チームでナレッジを活用できます。
3. データマイニングツール
データマイニングツールとは、蓄積した膨大なデータを統計学や人工知能などを用いて分析し、企業にとって価値のあるものを見出すツールです。
データマイニングツールを活用すれば、データを分析して見出したノウハウや知見を経営戦略や営業支援に役立てられます。
4. ヘルプデスクツール
ヘルプデスクツールとは、顧客からのお問い合わせへの対応を効率化できるツールです。
お問い合わせ内容をExcelで管理した場合、過去にもあった問い合わせを探すのに手間がかかります。
ヘルプデスクツールを利用すれば、データベースから自動的にFAQを作成できるため、効率的に対応できます。
また、電話対応するスタッフによって受け答えが変わる事態を防ぐことも可能です。
5. 文書管理システム
文書管理システムとは、電子化した文書を保管、活用するためのシステムです。
文書をバラバラに保管すると、必要な文書の保管場所が分からなくなり、効率的に活用できない可能性がありますが、文書管理システムを利用すれば、必要な情報をいつでも取り出すことができます。
文書管理システムでナレッジベースを構築すれば、書類を探す手間も省けます。
必要な書類はシステム上で確認できるため、リモートワークを導入している企業にとっても役立つでしょう。
6. 社内Wikiツール
社内Wikiツールとは、社内用Wikipediaのようなもので、社内の情報や業務のノウハウ、マニュアルなどの知識を蓄積・共有できます。
社員が持つ知識やノウハウを一元化し、誰でも知りたい情報に簡単にアクセス可能です。
また、社員であれば誰でも自由に書き込めるようにすれば蓄積・共有をより効率的に進められるでしょう。
ナレッジベースとは企業の大切な知的資産! 共有・活用して業務を効率化しよう
ナレッジベースは、個人の知識、経験、ノウハウを集約したデータベースであり、企業にとって重要な知的財産です。
社内で共有・活用することで、生産性向上や業務効率化が期待できます。
また、業務の属人化を防ぎ、特定の人材への依存を軽減できます。
ナレッジベースは、顧客からの問い合わせ対応にも有効です。
よくある質問とその回答を蓄積しておけば、顧客自身で問題を解決できるようになり、問い合わせ件数の削減や担当者の負担軽減にもつながります。
さらに、ナレッジベースをチャットボットと連携させることで、社内からの問い合わせ対応も自動化できます。
情報システム部、総務部、人事部など、他部署からの問い合わせが多い部署では、社員が自分で情報を探せるチャットボットの導入が効果的です。
Difyでは、RAGを活用した社内用チャットボットを容易に導入できます。
マニュアルなどを登録すれば、その情報を基にチャットボットが回答を生成します。
社内問い合わせ対応の自動化により、業務効率化を図れるため、よりコア業務へ集中できるようになるでしょう。
ツール連携による業務自動化をご検討中のご担当者さまは、ぜひDifyの利用をご検討ください。
 山本 豊
山本 豊Difyライセンス・支援サービスの営業責任者。
連絡先:dify@tdse.jp

お問い合わせはこちら

資料ダウンロードはこちら