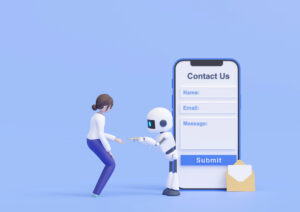-
- 投稿日
- 2025.03.27
-
- 更新日
- 2025.03.27
近年は多様な働き方に対応する企業が増え、以前より情報共有の必要性が高まっています。
業務効率や生産性向上のために、ナレッジシェアの必要性を感じている方も多いでしょう。
本記事では、ナレッジシェアに取り組むメリットや、社内で推進する方法などを解説します。
ただし、ナレッジシェアに取り組み始めても、必ず社内で定着するわけではありません。
そのため、失敗につながる原因と対策方法についても知っておくことが大切です。
成功させるポイントと合わせて参考にしてください。
目次
ナレッジシェアとは?
ナレッジシェアとは、社員一人ひとりが持つ知識や経験、ノウハウといった「ナレッジ」を組織内で共有し、有効活用する取り組みです。
ビジネスにおけるナレッジとは、単なる情報ではなく、業務に役立つ付加価値のある知識や経験、成功事例などを指します。
ナレッジシェアを推進することで、個人の持つ貴重な知識が組織全体の財産となり、業務効率の向上や新たなイノベーションの創出が期待できます。
特に、人材の流動性が高まっている現代において、個人の知識を組織に蓄積し、共有する環境の整備は不可欠です。
また過去の失敗事例やその対策を共有することで、経験から学び成長し続ける組織作りにも役立ちます。
ナレッジベースとの違い
ナレッジ関連の用語はナレッジシェア以外にもいくつかあります。
「ナレッジベース」とは、企業や社員個人が持つ業務に関わる知見やノウハウをデータベース化し、検索しやすく整理したものです。
ナレッジマネジメントのツールとして利用できます。
ナレッジシェアは知識の共有ですが、ナレッジベースは知識の蓄積という意味の違いがあります。
ナレッジマネジメントとの違い
「ナレッジマネジメント」とは、企業や社員個人が持つ業務に関わる知見やノウハウを集約して管理し、活用するための経営手法です。
ナレッジシェアは企業にとって有益な知識の共有を意味しますが、ナレッジマネジメントは集めた情報を蓄積するだけでなく、活用しやすいように管理する仕組み作りを意味します。
ナレッジシェアが注目される理由
近年、ナレッジシェアが注目されている理由には、主に次の2つが挙げられます。
人材の流動性が高まっている
ナレッジシェアが注目される理由の一つには、人材の流動性が高まっていることが挙げられます。
現代は終身雇用が崩壊しつつあり、転職するのが当たり前のようになっています。
優れた知見やスキルを持つ人材が他社に流出するのは、企業にとって大きな痛手です。
退職時に知識がきちんと引き継がれないと、その知識やノウハウは失われてしまいます。
しかし、個人の持つ知識やノウハウを組織内で共有し蓄積しておけば、他の社員へスムーズに引き継ぐことができます。
このように、近年は人材の流動性が高まっていることから、人材が流出しても企業活動に影響を及ぼさないよう、個人の知識を組織内で共有する環境の整備が必要です。
働き方の多様化
ナレッジシェアが注目される理由には、働き方の多様化も関係しています。
現代は生活環境やライフスタイルに合わせてテレワークや時短勤務、フレックス制度など、さまざまな働き方を導入する企業が増えています。
多様な働き方の導入は社員のモチベーションアップにつながりますが、仕事をする上ではコミュニケーションが課題です。
これまで自然と共有できていた情報が、伝わりにくくなることがあるからです。
テレワークは、オフィスに出社して仕事するときのように、気軽に質問や相談ができません。
そのため、業務効率や情報伝達のスピードが低下するケースがあります。
そこで業務に必要な知識やノウハウを組織内で共有するナレッジシェアに注目が集まっています。
オフィス以外の場所から必要な情報を取り出せるため、作業をスムーズに進めることが可能です。
ナレッジシェアに取り組むメリット
企業でナレッジシェアに取り組むと、主に次のようなメリットが得られます。
業務効率の向上
一つ目のメリットは、業務効率の向上です。
業務に関係する知識や手順などを一元管理し、情報を引き出せるようにしておけば、必要なときに必要な情報が迅速に手に入ります。
社員はマニュアルや手順書を参照しながら作業を進められるため、業務効率が向上します。
分からないことがあるたびに、他の担当者に質問するのは非効率です。
形式化されたナレッジがあれば、教える側も知識を習得する側も業務をスムーズに進められます。
生産性の向上
二つ目のメリットは、生産性の向上です。
社員一人ひとりが日々の業務で得た知識や経験を持っています。
社員が個々に持つ情報を共有することで、組織全体の生産性が向上するでしょう。
また、去の成功例や失敗例を共有すると、同じ問題に対して何度も失敗することを防げます。
さらに、優秀な社員が持つ優れたスキルやノウハウを共有すれば、経験に関わらず誰もが高い成果を出せるようになるでしょう。
属人化の解消
三つ目のメリットは、属人化の解消です。
業務が属人化すると、特定の社員の不在時に、業務の停滞や遅延が起こってしまいます。
多くの企業が属人化を解消するための施策を講じていますが、社内で情報共有の仕組みが整備されていないことも属人化の原因の一つです。
特定の従業員が持つ知識やノウハウを組織内で蓄積し、誰もがアクセスできるように共有すれば、その担当者が不在でも他の人が一定の品質で対応できます。
また担当者の退職と同時にナレッジを失う心配もありません。
属人化の解消によって、特定の社員に依存しなくて済むため、業務負担の偏りや人材不足の解消にもつながります。
人材育成や引き継ぎがスムーズになる
四つ目のメリットは、人材育成や引き継ぎがスムーズになることです。
業務に必要な知識やノウハウをマニュアル化しておけば、教育係の教え方に違いが生じることもありません。
分からないことはいつでも自身で確認できるため、教育係が常に付いて指導する必要がなくなり、人材育成にかかる時間やコストを削減できます。
またナレッジシェアを行っていれば、異動や退職によって後任者に引き継ぎが必要な際も、引き継ぎ資料の作成や細かな説明が必要なくなります。
引き継ぎにかかる時間を大幅に短縮できる上に伝達漏れもなくせるでしょう。
迅速な問題解決
五つ目のメリットは、迅速な問題解決につながることです。
ナレッジシェアによって、過去に経験した問題と同じようなことが起こったときに、適切な解決策を迅速に見つけられます。
問題解決にかかる時間を短縮できるため、業務の停滞を大幅に抑えられます。
イノベーションの促進
6つ目のメリットは、イノベーションの促進です。
個人や部署の中で埋もれていた知識が組織内で共有されると、新しいアイデアを生み出すことがあります。
異なる部署の知識が組み合わさることで、新たな製品やサービスが生まれる可能性もあります。
共有した方が良い主なナレッジ
さまざまな種類のナレッジがありますが、組織で共有した方が良いナレッジには主に次の3種類が挙げられます。
マニュアル・手順書
業務に必要な知識・プロセスを記したマニュアルや、ツールの手順書などのナレッジを共有すれば、社員の誰もが必要な情報をいつでも調べられます。
分からないことを知識がある人に教わる必要がなくなるため、生産性の向上を図れます。
他部署からの問い合わせが多い総務部や情報システム部は、マニュアルや手順書の共有によって問い合わせに対応する時間を大幅に削減できるでしょう。
成功事例
成功事例を共有すれば、過去の事例と同じような事案が起きたときや、新たな取り組みを行う際に参考になるでしょう。
他部署の成功事例がヒントになることもあるため、組織全体の生産性やスキル向上につながります。
専門知識
専門的な知識が必要な部署のナレッジを共有すれば、特定の社員に業務を依存することがなくなり、属人化や人材不足の解消につながります。
新人やその業務を担当したことがない社員でも、ナレッジを確認しながら作業できるため、業務がより円滑に進みます。
ナレッジシェアを推進する方法
社内でナレッジシェアに取り組む際は、計画的に進めましょう。
ナレッジシェアを推進する方法を解説します。
1. 目的を明確にする
ナレッジシェアを始めるときは、まず目的を明確にしましょう。
目的が曖昧なままで取り組み始めても、どのような知識やノウハウを共有すれば良いか分からないため、ナレッジが集まらない可能性があります。
また情報が多く集まったとしても、業務改善やスキルアップの役に立たないかもしれません。
どのような目的でナレッジ共有し、その結果、どのような目標を達成したいのか決めておきましょう。
目的が明確になれば、どのようなナレッジを共有すべきか明確になります。
2. ナレッジ共有の範囲を決める
次にナレッジ共有の範囲を決めましょう。
共有すべきナレッジ範囲を決めておけば、不必要なナレッジが集まることを防げます。
業務プロセスや必要なスキルを分析してナレッジ共有の範囲を決め、優先順位を付けて欲しい情報が見つかりやすいようにしておきましょう。
3. マニュアルの作成
ナレッジシェアは、社員個人が持つナレッジの蓄積と、必要なナレッジを簡単に見つけ出せる仕組み作りが大切です。
ナレッジを登録する方法や検索する方法などをマニュアル化して整理し、誰もが活用しやすい環境を整えましょう。
マニュアルはWordやExcelなど身近なツールで作成可能です。
WordやExcelは社内の多くの人が操作方法を理解しているため、手軽にナレッジシェアを推進できます。
ただし、WordやExcelで作成した場合、更新した内容をリアルタイムで共有できないことがデメリットです。
更新のたびに再配布が必要になるため、手間もかかります。
また、更新前の情報を参照して仕事を進めてしまうリスクにも注意が必要です。
WordやExcelは手軽に導入しやすいツールですが、労力がかかり、ナレッジの共有がスムーズにいかない可能性もあります。
クラウド上で運用するツールの活用も検討しましょう。
4. ツールの導入
ナレッジシェアの推進には、ツールの導入が効果的です。
ナレッジシェアツールには、ナレッジの整理や共有、検索などの機能が備わっており、組織が蓄積した知識や経験を効率良く共有できます。
ツールを選定する際は、使いやすさを重視して選ぶと社内に浸透しやすいでしょう。
使いにくければ、せっかくツールを導入しても使われなくなる可能性があります。
ナレッジシェアの効果を引き出すためにも、使いやすさを重視して選ぶことが重要です。
無料のトライアル期間が設けられたツールもあるので、使用感を確認してから選ぶと良いでしょう。
ナレッジシェアを成功させるポイント
ナレッジシェアを成功させるためのポイントを3つ挙げます。
推進するリーダーの選出
ナレッジシェアを推進するために、まずはリーダー(担当者)を決めましょう。
個人がそれぞれ努力してもナレッジシェアは進みません。
プロジェクトを円滑に進めるためのリーダーが必要です。
リーダーはナレッジシェアのメリットや必要性を全社員に伝え、積極的な参加を促す必要があります。
また定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて改善策を講じる役割もあります。
さらに、混乱を避けるためにルールの作成も必要です。
リーダーはある程度業務経験のある社員から選ぶと良いでしょう。
社員に重要性を伝える
ナレッジシェアの取り組みを成功させるには、社員の協力が不可欠です。
積極的に協力してもらうためにも、最初にナレッジシェアの重要性を伝えましょう。
重要性を伝えておかなければ、積極的な協力を得られない可能性があります。
また社内で定着させるためにも、定期的に教育プログラムなどを実施して、組織全体で情報共有に参加する環境を整備しましょう。
常に最新情報に更新する
ナレッジシェアは、常に最新情報に更新しておくことが重要です。
古い情報に基づいて業務に取り組んだ結果、行き違いが生じてしまい顧客の信頼を損ねる恐れがあります。
ナレッジは常に新しい状態に保ち、更新や削除した際は周知できるような仕組み作りをしておきましょう。
ナレッジシェアが失敗する原因と対策
ナレッジシェアに取り組んだからといって、ナレッジの共有がスムーズに進むとは限りません。
ナレッジシェアの失敗につながりやすい原因と、その対策方法を解説します。
メリットが伝わっていない
ナレッジシェアのメリットが社員に伝わっていなければ、社内で定着しません。
最初に導入目的やメリット、必要性を十分に説明して理解してもらいましょう。
メリットがうまく伝わらなければ、ナレッジを共有しようというモチベーションにつながらない恐れがあります。
メリットを伝えるには、リーダーが必要です。
リーダーシップに優れた社員をナレッジシェアのリーダーに選定し、なぜ重要で具体的にどのようなメリットがあるか社員に伝えてもらいましょう。
知識を共有したくなる仕組みが作られていない
優秀な社員の優れた知見やノウハウを共有すれば、他の社員のスキルアップにつながります。
しかし、知識を共有したくなる仕組みが作られていない場合、優秀な社員が自身のノウハウを積極的に提供しようとは考えないかもしれません。
優れたノウハウの共有は、組織全体の生産性を高めます。
しかし、優秀な社員が自身の優れたノウハウを提供した結果、何の見返りもないのであれば、ナレッジシェアに対するモチベーションが続かない可能性があります。
価値あるナレッジの共有を評価制度に組み込む、インセンティブを支払うなど、知識を共有したくなる仕組みを作ることが大切です。
ツールが使いにくい
ツールを選ぶときは、使いやすさを重視して決めることが大切です。
いくら有益な情報を蓄積しても、検索性が悪ければ、欲しい情報を見つけ出すのは困難です。
使いにくいツールでは利用されなくなってしまうため、ナレッジの共有が定着しません。
使いやすさにこだわってツールを選びましょう。
ナレッジシェアに役立つ主なツール
先述のように、ナレッジの量が多い場合や、社内全体で共有する場合、ツールを活用するのが便利です。
ナレッジシェアに役立つ代表的なツールを2つご紹介します。
社内Wiki
社内Wikiとは、組織で蓄積したノウハウやデータを一元管理し、リアルタイムで共有できるツールです。
社内の誰でも編集や閲覧ができるため、常に最新情報を維持できます。
チャットボット
チャットボットとは、よくある質問を登録しておくと、自動で受け答えができるツールです。
ナレッジをFAQとして登録すれば、社員はチャットボットを活用して必要な情報を得られます。
会話をするような感覚で質問すれば回答が提示されるため、自分で検索して探す必要がありません。
チャットボットによるナレッジシェアが定着すれば、問い合わせへの対応時間が軽減されるため、サポート業務の負担を減らせます。
ツールを選ぶ際のポイント
ナレッジシェアのツール選定は、次の3つをポイントにしましょう。
導入目的に合う
一つ目は、ナレッジシェアの導入目的に合っていることが挙げられます。
課題を解決するためには、どのような機能が必要か検討して選びましょう。
検索性の高さ
二つ目は、検索性の高さです。
知りたい情報にすぐたどり着けるように、検索のしやすさを重視して選びましょう。
知りたい情報が見つかりにくいと、ツールを利用する人が減ってしまう恐れがあります。
知りたい情報があれば迅速に情報を引き出せるよう、検索性の高いツールを選びましょう。
セキュリティ性の高さ
三つ目は、セキュリティ性です。
ナレッジシェアのツールを選ぶときは、他のクラウドサービスを選ぶときと同じように、セキュリティ性の高さも重視して選びましょう。
ナレッジシェアのツールは企業の重要な情報を蓄積するため、セキュリティ対策は重要です。
万が一、機密情報が漏えいすれば、大きな問題になってしまいます。
大切な情報を守るためにも、アクセス権限を設定して情報漏えいを防げるツールを選びましょう。
ナレッジシェアで組織全体の生産性を向上させよう
ナレッジシェアは、社員が業務を通して培った知識やノウハウなどを、個人の中で埋もれさせないように組織で共有し、生産性や業務効率の向上を図る取り組みです。
社内で導入する際は、目的や重要性を社員に理解してもらうことが重要です。
ただし、全社員が協力的になってくれるとは限らないため、優秀な社員に価値あるナレッジを提供してもらうための仕組み作りも考えましょう。
ナレッジシェアにはシステムやツールを利用するのが効果的です。
ツールを選定する際は、導入目的に沿っていることはもちろん、検索性やセキュリティ性が高いものを選びましょう。
例えばチャットボットによくある質問を登録しておけば、まるで会話するような感覚で回答が提示されるため、誰かに質問しなくても自身で迅速に解決可能です。
新人教育の効率化にも役立つでしょう。
AIを用いたアプリ開発には「Dify」の活用がおすすめです。
プログラミングの知識がなくても、AIチャットボットやAI機能を搭載した社内Wikiを開発できます。
ナレッジシェア推進のためにAIツールの導入・開発を検討中の担当者の方は、お気軽にお問い合わせください。
 山本 豊
山本 豊Difyライセンス・支援サービスの営業責任者。
連絡先:dify@tdse.jp

お問い合わせはこちら

資料ダウンロードはこちら