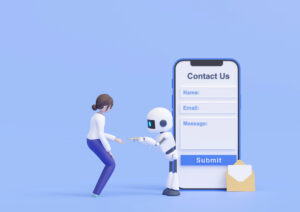-
- 投稿日
- 2025.03.27
-
- 更新日
- 2025.03.27
企業が生産性を向上させるには、業務効率化によってムリ・ムダ・ムラを排除することが重要です。
しかし、業務効率化を実施するに当たって、どこから手を付けるべきか悩む方は多いでしょう。
まずは業務の可視化によって課題を特定し、その上で適切な方法で業務効率化を実施する必要があります。
本記事では、業務効率化が重要な理由や具体的な方法について解説します。
併せて、業務効率化のアイデア・事例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
業務効率化とは?
業務効率化とは、業務における「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、効率良く業務を遂行するための取り組みです。
単に作業のスピードを上げるだけでなく、継続的に質の高い成果を生み出すことを目指します。
具体的には、手作業で行っている業務を自動化したり、情報を一元管理したりすることで、作業の正確性とスピードを向上させます。
労働力不足が深刻化している日本では、業務効率化は不可欠です。
業務の自動化やITツールの導入、業務フローの見直しなどにより、限られた人員でも最大限の成果を創出する工夫が今後ますます重要となります。
業務効率化により、従業員がより重要度の高い業務や自己啓発に時間を費やせるようになれば、スキルアップやモチベーション向上も期待できるでしょう。
生産性向上との違い
業務効率化と生産性向上は混同されがちですが、目的と手段が異なります。
業務効率化は、既存の業務から「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、改善することです。
一方、生産性向上は、従業員数や労働時間といったインプットに対して、より多くのアウトプット(成果)を生み出すことを目指します。
業務効率化は、生産性向上を実現するための手段の一つです。
業務効率化によって労働時間を短縮できれば、結果的に生産性も向上します。
しかし、業務効率化で投入資源を減らした結果、生産量も減少する可能性もあります。
両者の違いを理解し、目的に応じた施策を実施することが重要です。
業務効率化の重要性
近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、業務効率化の重要性はますます高まっています。
業務効率化に取り組む前に、その重要性を理解しておきましょう。
- 労働人口の減少
- 働き方の変化への対応
労働人口の減少
業務効率化が求められる背景には、日本の労働人口の減少があります。
少子高齢化が急速に進む日本において、労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は減少傾向です。
総務省統計局の「労働力調査」によると、2023年の労働力人口は平均で6,957万人と、前年に比べて39万人の増加となり2023年に引き続き2年連続増加しているものの、長期的な減少傾向は変わらないといわれています(※)。
労働人口の減少は、企業の人材確保を困難にするだけでなく、経済全体の成長を鈍化させる要因です。
消費の担い手である現役世代が減少することで、国内の消費市場が縮小し、企業の売上低下や経済の停滞を招く可能性があります。
このような状況下で、企業が競争力を維持し、持続的な成長を実現するためには、限られた労働力で最大限の成果を上げる業務効率化が不可欠となっています。
※参考:総務省.「労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約」.https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/youyaku.pdf ,(参照2025-02-27).
働き方の変化への対応
業務効率化が求められるもう一つの背景として、働き方改革の推進が挙げられます。
働き方改革によって、時間外労働の上限規制や有給休暇取得の義務化が進み、企業は法令順守と従業員のワークライフバランスの両立を求められています。
正確な勤怠管理や人員配置の見直しによって、長時間労働の是正に取り組む企業が増えています。
また新型コロナウイルス感染症の拡大は、働き方に大きな変化をもたらしました。
新しいツールの導入や社内インフラの整備、業務フローの見直しなどに対応するためにも、業務効率化は重要な手段となっています。
業務効率化を実施するメリット
業務効率化を実施するメリットは以下の通りです。
業務効率化を検討している方は、メリットを把握しておきましょう。
- 生産性の向上が期待できる
- 従業員のモチベーションを向上させられる
- コストの削減が期待できる
- 離職率の低下につながる
生産性の向上が期待できる
業務効率化を実施することで、生産性向上が期待できます。
例えば、伝票処理やデータ入力などの定型業務を自動化することで、従業員はより重要なコア業務への集中が可能です。
これにより、少ないインプットで多くのアウトプットが得られ、組織全体のパフォーマンスが向上します。
また既存業務の見直しを行い、「ムリ」や「ムラ」を改善できれば、業務にかかる時間や費用を抑えることも可能です。
結果として、生産性向上にもつながります。
業務効率化によって「ムダ」の排除を続けることで、生産性向上も実現できます。
業績を向上させたい企業にとって、業務効率化は重要な戦略です。
従業員のモチベーションを向上させられる
業務効率化は、企業と従業員の双方にメリットがあります。
企業は少ないリソースで成果を上げ、従業員はモチベーションの向上を期待できます。
業務フローの見直しや情報共有ツールの導入により、承認プロセスや連携が円滑化し、機械的な作業を削減可能です。
従業員は付加価値の高い創造的な業務に集中でき、チーム全体の士気が高まります。
従業員はワークライフバランスを実現し、モチベーションと満足度を高められるでしょう。
業務効率化によって従業員に働きやすい環境と働きがいを提供することで、業績向上と企業の利益にもつながります。
コストの削減が期待できる
業務効率化によって、コスト削減が期待できます。
非効率な業務による長時間労働は人件費の無駄遣いを招き、利益を圧迫する要因です。
限られたリソースで利益を最大化するには無駄な業務を削減し、効率的な業務プロセスを構築する必要があります。
例えば、書類作成業務で発生するコストは従業員の人件費や紙代、インク代、光熱費などです。
業務効率化により不要な業務を特定し、コストを削減することで他の事業にリソースを投入できます。
業務効率化は人的リソースに余裕を生み出すため、企業が新規事業へ挑戦する場合にも欠かせません。
離職率の低下につながる
業務効率化は、離職率の低下にもつながります。
労働時間の適正化とストレスの軽減によって働きやすい環境を提供できれば、従業員の定着率向上も可能です。
人材確保が困難な現代において、不適正職場環境は離職増加を招きます。
特に優秀な人材は、より良い環境を求めて離職する傾向です。
健康的な職場環境は、有能な人材が長く活躍するための重要な要素です。
また業務効率化は時短勤務やテレワークなど、柔軟な働き方を実現します。
子育てや介護など、時間的な制約のある従業員でも働き続けられる環境の提供が可能です。
業務効率化を実施する方法
業務効率化を実施する際は、計画を立ててスムーズに進めることが重要です。
自社で取り組む前に、具体的な方法を把握しましょう。
- 全ての業務をリストアップする
- 業務における課題を特定する
- 改善策を検討する
- 業務効率化を実行する
- 効果の検証と測定を実施する
1. 全ての業務をリストアップする
業務効率化の第一実施する際は、まず現状把握と課題の可視化を行いましょう。
この時に、全ての業務内容を詳細にリストアップし、業務の全体像を把握することが重要です。
業務内容を細分化し、所要時間も確認することで、重要度や時間消費の多いタスクが明確になります。
各業務のフローや関連部署、担当者をリスト化し、効率化の対象となる業務を特定しましょう。
日常的に行われる反復作業や手間のかかる作業に注目し、抜け漏れなく業務をリストアップしましょう。
2. 業務における課題を特定する
リストアップした業務を基に、現場の問題点や課題を特定します。
従業員からのフィードバックを積極的に取り入れ、現場の声を反映させましょう。
実際に業務を行う従業員の意見を聞くことで、効率化の妨げとなる要因や改善が必要な部分が明確になります。
課題を特定することで、効率化のための具体的な目標設定が可能です。
そして、手作業で時間がかかる業務、重複業務、不必要な反復作業などをピックアップしましょう。
3. 改善策を検討する
業務の課題を特定したら、具体的な改善策と実施スケジュールを計画します。
スケジュールは、進捗を可視化しやすい形で作成し、ガントチャートやプロジェクト管理ツールを活用しましょう。
各改善策の開始日と終了日を明示することで、進捗管理が容易になります。
業務の改善策を検討する際は、省いても問題ない工程はないか、別の方法で代用できないかなど、効率的に進める方法を考えましょう。
改善策にはシステム導入や自動化、他部門連携など、多様な選択肢があるため、状況に応じて方法を選択しましょう。
4. 業務効率化を実行する
計画したスケジュールに従い、改善策を実行します。
計画通りに進んでいるか定期的にチェックし、必要に応じて微調整を行いましょう。
実施過程で発生する問題やトラブルに迅速に対応するには、小まめにフィードバックの機会を設けることが重要です。
チーム全体で進捗を共有し、柔軟に対応することで、計画の成功確率を高められます。
また重複工程の削減や作業手順の見直しを行い、優先度の高い業務から取り組んでください。
計画実行時には所要時間を記録しておくと、効果検証に役立ちます。
5. 効果の検証と測定を実施する
計画の実行後は、改善前後の効率化の効果を振り返ります。
具体的にどの改善策が効果的だったか、あるいは効率化できなかった原因を分析し、さらなる改善策を検討しましょう。
KPIを設定して目標達成度を評価することで、効果の有無を確認します。
効果が低い場合は、原因分析と新たな改善策が必要です。
業務効率化は一度きりの取り組みではなく、定期的な振り返りと改善を行わなければなりません。
定期的な評価とフィードバックを繰り返しましょう。
業務効率化のアイデア・事例
業務効率化では、さまざまなアイデアから自社に合ったものを取り入れることが重要です。
ここでは、どのような事例があるのかを紹介します。
- ワークフローの見直し
- 業務マニュアルの作成
- データベースの整備
- 業務の自動化
- システムの活用
ワークフローの見直し
業務効率化には、業務プロセスの分析と不要な業務の削減が効果的です。
既存の業務フローを見直し、無駄なステップや重複作業を特定しましょう。
例えば、同じデータを複数回入力する作業や複雑な承認プロセスは、簡略化または削除することで業務をスムーズにできます。
また、無駄な業務や会議がないかを常に意識することも重要です。
前任者の業務をそのまま引き継いでいる場合、見直しにより削減できる業務が見つかる可能性があります。
会議に関しても定例という理由だけで行わず、報告だけで済む場合は別の手段がないかを検討しましょう。
業務マニュアルの作成
業務効率化には、業務マニュアルの作成が有効です。
業務が属人化している場合や品質にムラがある場合は、マニュアルの作成を検討しましょう。
マニュアルは、誰が見ても理解できる分かりやすい内容にすることが重要です。
他部署の同僚や新入社員でも理解できる内容を目指しましょう。
マニュアル作成により、業務の標準化と一貫性を維持できます。
詳細な手順をまとめることで、新人研修が容易になり、教育コストの削減が可能です。
また、マニュアルは認識違いによるミスを防ぐ際にも役立ちます。
定期的な見直しと更新によって、常に新しい情報に基づき業務を処理できます。
データベースの整備
業務効率化には、情報集約とデータベース化が有効です。
業務に必要な情報やノウハウを集約し、データベース化することで、情報共有と業務連携を円滑化できます。
データベースの構築により、データ検索と更新が迅速かつ正確に行えます。
社内に散在する情報を一元管理し、必要な情報に迅速にアクセスできる環境の提供が可能です。
顧客情報や製品情報、業務プロセスなどのデータを一元管理することで、部門間の連携を強化できます。
定期的なデータ更新とバックアップにより、データの正確性を維持しましょう。
また、データベースの整備を実施する際は、管理システム導入も検討しましょう。
業務の自動化
業務効率化には、RPAなどの自動化ツールの活用が効果的です。
RPAはデータ入力や資料作成などの反復作業を自動化し、時間とリソースを節約できます。
RPA導入により、メーラーやブラウザ、基幹システムなど、複数アプリにまたがる操作も自動化が可能です。
これにより、人的ミス削減と処理速度向上が期待できます。
また、営業支援ツールやコミュニケーションツールも業務効率化を推進します。
顧客管理や進捗管理を簡単にし、リモートワーク環境でもスムーズな連携の実現が可能です。
自動化ツールは単独でも効果がありますが、複数のツールを組み合わせることで効率化の効果を高められます。
システムの活用
業務効率化を実現するためには、自社の課題に合ったツールの導入が効果的です。
例えば、コミュニケーションの円滑化にはチャットツールが役立ちます。
リアルタイムでのやり取りが可能となり、業務のスピードが向上するでしょう。
またデータベースツールを活用すれば、フォルダやファイルの共有が容易になり、検索性も高まります。
営業支援システムを導入すると、顧客情報や対応履歴を一元管理でき、担当者の変更があってもスムーズな引き継ぎが可能です。
適切なツールを選定し、業務の効率化を進めましょう。
業務効率化の実現にはツールの導入を検討しよう
企業が働き方改革や労働人口の減少に対応するには、ムリ・ムダ・ムラを排除する業務効率化が欠かせません。
業務効率化の実施で従来のフローを見直すことで、生産性の向上やコストの削減が期待できます。
ただし、業務の課題を特定し、自社のニーズに合った業務効率化の実施が重要です。
TDSE株式会社では、業務効率化を目的とした生成AIの導入サポートを提供しています。
ツールの選定に悩む担当者の方は、お気軽にご相談ください。
 山本 豊
山本 豊Difyライセンス・支援サービスの営業責任者。
連絡先:dify@tdse.jp

お問い合わせはこちら

資料ダウンロードはこちら