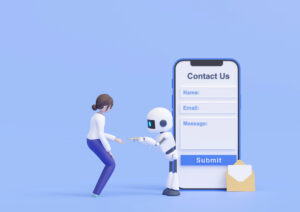-
- 投稿日
- 2025.03.27
-
- 更新日
- 2025.03.27
デジタル化の波が企業経営の各分野に広がる中、バックオフィス業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)が注目を集めています。
これは、経理や人事、法務といったバックオフィス業務にITツールやAIを取り入れ、業務の効率化とコスト削減を目指す取り組みです。
本記事では、バックオフィスDXの重要性やメリット、具体的な進め方などについて詳しく解説します。
バックオフィス業務の業務改革を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
バックオフィスDXとは?
バックオフィスDXとは、経理や人事、法務などの業務にITツールやAIを導入し、デジタル化を進めることで業務効率化やコスト削減を図る取り組みです。
従来の紙ベースの業務をデジタル化すれば、データの管理が容易になり、事務作業の負担軽減や入力ミスの削減が期待できます。
また、これまでリモートワークが難しかった職種でも、多様な働き方が実現しやすくなります。
ただし、単にツールを導入するだけではDXは進められません。
バックオフィスDXを成功させるには、業務をデジタル化した上で、業務プロセスの見直しや企業全体の変革につなげる視点が重要です。
バックオフィスDXが重要な理由
バックオフィスDXが重要とされる背景には、次のような企業の抱える課題があります。
- 2025年の崖問題
- 業務負担の大きさ
- 属人化の問題
以下で詳しく説明します。
2025年の崖問題
バックオフィスDXは、企業の業務効率化だけでなく「2025年の崖」問題への対応としても注目されています。
2025年の崖とは、老朽化した既存システムを維持し続けることで発生するリスクの総称です。
具体的には、保守運用コストの増加やセキュリティの脆弱性、最新技術への適応遅れなどが挙げられます。
これらの問題を放置すると、企業の競争力や利益の低下につながるおそれがあります。
そのため、既存システムの刷新やクラウド化など、バックオフィスDXによる抜本的な改革が必要です。
業務負担の大きさ
バックオフィスには専門知識を持つ人材が求められるため、人材確保が困難な状況になりやすいという特徴があります。
一人当たりの業務量が多く、業務担当者の負担が大きくなっている会社も多いでしょう。
特に中小・ベンチャー企業では、バックオフィス部門に十分な人員を配置できず、兼任しているケースが目立ちます。
バックオフィス業務が回らなくなると、会社全体に悪影響が及ぶ可能性があります。
そのため、バックオフィスDXや業務効率化が不可欠です。
属人化の問題
バックオフィス業務の属人化も解決すべき課題の一つです。
バックオフィス業務では同じ担当者が長年業務を行っていることが多く、不在時や退職時に引継ぎが困難というケースがあります。
特に、エクセルやコーディングで管理された業務は引継ぎが難しく、業務停滞のリスクが高まる要因になります。
業務内容がブラックボックス化していると、担当者の退職に伴い思わぬトラブルが生じる可能性もあるでしょう。
これらの課題を解決するためにも、ITやデジタル技術を活用したバックオフィスDXが不可欠です。
バックオフィスDXのメリット
バックオフィスDXには以下のメリットがあります。
自社でDX化を検討している方は、メリットを把握しておきましょう。
- 生産性の向上が期待できる
- ヒューマンエラーの減少を実現できる
- コスト削減につながる
- 人材を確保しやすくなる
- 従業員の満足度を向上させられる
生産性の向上が期待できる
バックオフィスDXの導入によって、生産性の向上が期待できます。
RPAやクラウドツールを活用し、定型業務を自動化できれば、従業員の作業時間を短縮できるためです。
業務フローの整理と標準化が進めば、誰でも一定の質と効率で業務に対応できるようになります。
さらに業務を「見える化」できれば、チーム連携がより円滑になり、バックオフィス全体の効率が向上するでしょう。
ヒューマンエラーの減少を実現できる
バックオフィスDXは、ヒューマンエラー防止と業務精度向上にも役立ちます。
バックオフィス業務は細かな作業が多く、正確性が求められる業務です。
特に経理業務では、請求金額の誤りや支払遅延は企業の信用に関わる問題です。
そこで、バックオフィスDXを推進し業務を自動化することで、業務精度の向上とリスクの低減につながります。
RPAなどのデジタルツールで定型業務を自動化できれば、業務効率が高まるだけでなく、作業品質の標準化も実現できます。
データ入力などの事務作業におけるケアレスミスも削減できるでしょう。
コスト削減につながる
バックオフィスDXには、コスト削減につながるというメリットもあります。
入力作業やチェック業務などを自動化することで、残業時間や人件費を削減できます。
IT化が遅れていた企業ほど、大きな効果が得られるでしょう。
また、入力作業の自動化やペーパーレス化により、印刷費用などの関連コストも削減できます。
初期投資は必要ですが、長期的に見れば投資額以上の効果が期待できるでしょう。
削減できた残業時間や年間コストから、DX化の効果を数値化しやすい点もメリットです。
人材を確保しやすくなる
バックオフィスDXを導入することで、テレワークなど多様な働き方に対応しやすくなるため、人材確保につながるというメリットもあります。
多様な働き方は求職者にとって魅力的な要素です。
柔軟な働き方を提示することで、求める人材を採用しやすくなるだけでなく、定着率向上も期待できます。
求職者に「柔軟に働ける会社」と認識されれば、企業イメージの向上も期待できるでしょう。
このように、バックオフィスDXの推進は、人材確保や企業イメージの向上にもつながるのです。
従業員の満足度を向上させられる
バックオフィスDXを導入することで、従業員の満足度の向上も期待できます。
勤怠管理や経費精算などの業務をオンライン化できれば、在宅勤務が可能となります。
柔軟な働き方は、従業員のワークライフバランスの改善や満足度の向上につながるでしょう。
また、業務効率化によって従業員の負担を軽減できれば、より働きやすい環境となり、離職防止にも役立ちます。
バックオフィスDXを進める具体的なステップ
バックオフィスDXを進めるための具体的なステップを解説します。
導入を検討している方は、流れを押さえておきましょう。
- バックオフィス業務を可視化する
- DXを進める業務を選定する
- 導入するツール・サービスを検討する
- 効果測定とPDCAを継続する
1. バックオフィス業務を可視化する
バックオフィスDXを推進する際は、現状分析と課題の可視化が必須です。
業務フローや作業内容、所要時間を洗い出し、経営者と現場担当者が共通認識を持つようにしましょう。
基本的に、大小問わず全ての業務を洗い出し、長期的に活用できる可視化資料を作成します。
ただし、全業務のDX化はコストがかかるため、優先順位をつけることが重要です。
優先順位は重要度・緊急度が高い業務、発生頻度の高い業務から検討しましょう。
例えば、人的ミスの発生が多い業務や、他の業務を圧迫している業務などが該当します。
また業務の可視化を行った結果、業務の進め方が担当者ごとに異なることが判明したした場合には、業務フローを標準化することでデジタル化や自動化が行いやすくなります。
業務標準化に関するセミナーも活用しながら、DX推進の基盤を構築しましょう。
2. DXを進める業務を選定する
バックオフィスの業務を可視化した後は、DX化の対象となる業務を選定します。
基本的に、事前に検討した優先順位を参考に効果が大きい業務から導入を検討するとよいでしょう。
ただし、効果が実感しにくい課題から取り組むと、社員のモチベーションが低下する可能性があります。
ある程度絞ったら、専門的な知識を持つ人に方針を確認してもらうのがおすすめです。
自社に専門家がいない場合、外部企業から提案を受けてアドバイスをもらいながら、DX化を進めるべき業務を選定しましょう。
3. 導入するツール・サービスを検討する
DX化を進める業務の選定が完了したら、必要なツール・サービスを導入しましょう。
多くのツールを同時導入すると社員が使いこなせず、DX化が停滞する可能性があります。
業務効率や効果の大きさを意識し、自社の課題解決につながるツールを選ぶことが大切です。
例えば、電話対応業務がDX化を進めるべき課題なら、電話業務特化型ソリューションを選定するとよいでしょう。
ツールには、クラウドサービスやオンプレミス型など、複数の選択肢があります。
バックオフィス業務の場合、汎用的なシステムやクラウドサービスを選ぶのがおすすめです。
機能や予算、サポート体制などを比較検討して、自社に合ったツール・サービスを選びましょう。
なお、DX化を進めるにはシステム導入に加えて、業務フローの見直しや従業員研修も必要です。
導入後すぐに最大のパフォーマンスが得られるとは限らないため、計画的な導入を心掛けましょう。
4. 効果測定とPDCAを継続する
ツール・サービスの導入後は、定期的な効果検証が必要です。
業務処理時間の短縮率やエラー発生率の減少、コスト削減額など、具体的な数値で導入効果を把握し、目標達成度を測定しましょう。
期待した成果が得られない場合は、原因を分析し改善策を検討します。
ツールの見直しや機能追加、運用ルールの調整など、状況に応じた対応が必要です。
このように、効果検証のサイクルを継続的に回すことで、バックオフィスDXの効果を引き出せます。
AIでできることとできないことを見極め、業務効率の向上を目指しましょう。
バックオフィスDXの具体的な取り組み
バックオフィスDXの具体的な取り組みには、以下の4つがあります。
自社に導入する際の参考として把握しておきましょう。
- ペーパーレス化の推進
- RPA・AIツールの活用
- クラウドシステムの導入
- アウトソーシングの利用
ペーパーレス化の推進
バックオフィスDXを推進する上で、ペーパーレス化は欠かせません。
紙ベースでの業務は、印刷費や紙代といったコストが発生するため、ペーパーレス化を進めることでコスト削減が可能になります。
また紙ベースで業務を行っていると、押印や署名のために出社が必要になるケースもあります。
これらは、テレワークが難しくなる要因の一つです。
オンライン上で業務を完結できるようになると、より柔軟な働き方が可能となる上、データの紛失リスクを軽減できます。
スキャンの活用や業務システムとの組み合わせによって書類を電子化し、ペーパーレス化を進めましょう。
RPA・AIツールの活用
バックオフィスDXを推進する手段として、RPA(Robotic Process Automation)の導入が効果的です。
RPAは定型業務を自動化するソフトウェアであり、データ入力や他システムとの連携などの作業を得意としています。
24時間稼働が可能なため、業務の効率化と生産性の向上につながるのも特徴です。
またRPAとAIを組み合わせることで、より高度な自動化が実現できます。
バックオフィスDXでは「自動化」が重要なポイントの一つであり、RPAの活用はその第一歩となるでしょう。
クラウドシステムの導入
クラウドシステムを導入すれば、オンラインでデータの保存や共有が可能となり、場所を選ばない働き方を実現しやすくなります。
勤怠管理や時間外労働の自動集計機能も、担当者の負担軽減につながるでしょう。
またクラウドサービスで事務作業をリモート化できれば、従業員の負担軽減が満足度向上につながり、離職率低下に期待できるのもメリットです。
さまざまなクラウドサービスが存在するため、DX化したい業務に合わせて適したサービスを選びましょう。
アウトソーシングの利用
バックオフィスDXを推進する際は、アウトソーシングの活用も有効です。
アウトソーシングとは、経理や人事、給与計算などのバックオフィス業務を外部の専門業者に委託することを指します。
これによって業務の属人化を防ぎ、人材不足の解消も可能です。
また業務負担の軽減によってコア業務に集中できるため、生産性の向上も期待できるでしょう。
ただし、委託先の実績やサポート体制はさまざまなため、慎重に選定することが重要です。
適切なアウトソーシングを活用し、業務効率化とDXの促進に取り組んでいきましょう。
バックオフィスDXのポイント
バックオフィスのDX化を実現するには、押さえるべきポイントがあります。
スムーズにDX化を進めるために、ポイントを理解しておきましょう。
- 具体的な目標を設定する
- スモールスタートを心掛ける
- 従業員にDX化の意義を周知する
具体的な目標を設定する
DXを推進する上で、「何を達成したいか」という具体的な目標設定は欠かせません。
漠然とした目標ではなく、業務効率の向上やコスト削減など、具体的な数値で測定可能な目標を設定することが重要です。
例えば「従業員の満足度を向上させる」といった目標ではなく、「業務時間を〇時間短縮する」といった具体的な数値目標を設定することで、より効果的な施策を打てます。
基準を設けることで予算の検討や結果に対する議論もできるため、仮の数値であっても目標を設定しましょう。
スモールスタートを心掛ける
バックオフィス業務は多岐にわたるため、一度に全てをDX化するのは困難です。
そのため、業務の優先順位を決め、スモールスタートを目指しましょう。
少しずつ導入し、成功事例や課題を振り返りながら範囲を広げていくことで、従業員の理解も得やすくなります。
導入のハードルが低い書類のデジタル化や、効果を実感しやすいチャットボットの導入から始めるのも有効です。
従業員にDX化の意義を周知する
バックオフィスのDX推進には、従業員の理解と協力が不可欠です。
従業員が混乱しないようDX化の目的と効果を丁寧に説明し、理解を深めましょう。
「そもそもDXとは何か」「どのような効果があるのか」といった疑問や「新しいシステムを覚えるのは面倒」といった抵抗感を抱く従業員もいるかもしれません。
理解が得られないままツールを導入しても、活用されずDX化が進まない可能性があります。
そのため、従業員にとってのメリットを具体的に説明し、理解を促すことが重要です。
ツール導入時には説明会やレクチャーを開催し、使い方のサポートを行いましょう。
バックオフィスDXで業務の負担を軽減しよう
バックオフィス業務において、企業が抱える課題を解決するには、DXが効果的です。
バックオフィスのDX化に取り組むことで、生産性の向上やコストの削減が期待できます。
ただし、バックオフィスのDX化はすぐに結果が出るものではありません。
まずはスモールスタートで様子を見て、可能な範囲でDXを拡大させていきましょう。
TDSE株式会社では、生成AIの導入サポートを提供しています。
生成AIを活用したバックオフィスDXを検討している担当者の方は、お気軽にご相談ください。
 山本 豊
山本 豊Difyライセンス・支援サービスの営業責任者。
連絡先:dify@tdse.jp

お問い合わせはこちら

資料ダウンロードはこちら